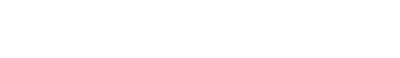Interview
大切なのは写真を軸に
様々な領域から吸収すること。
探求し続けられるテーマに
出会うための幅広い視野を。
大切なのは写真を軸に様々な領域から吸収すること。探求し続けられるテーマに出会うための幅広い視野を。