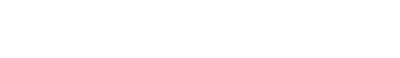直木賞作家 永井紗耶子さんによる特別講義 「インタビューと小説」「作者と読む『木挽町のあだ討ち』」 直木賞作家 永井紗耶子さんによる特別講義 「インタビューと小説」「作者と読む『木挽町のあだ討ち』」

2024年5月24日、大阪芸術大学9号館にて、第169回直木賞、第35回山本周五郎賞を受賞された永井紗耶子さんによる特別講義が行われました。当日は文芸学科の学生たちが数多く来場。「インタビューと小説」、「作者 永井紗耶子氏と読む『木挽町のあだ討ち』」と題した2つの講義を、文芸学科の小川光生教授とともに制作秘話や学生時代のエピソード、学生へのアドバイスなど、貴重なお話を披露してくれました。


5月24日。大阪芸術大学、9号館102号室。
永井紗耶子さんと会うのは、昨年の8月、第169回直木賞の授賞式以来だが、こんなふうに、2人でゆっくりと言葉を交わすのはいつぶりだろうかと考える。もしかしたら、数十年ぶりかもしれない。ただ、そんな時の流れを感じさせないほど、永井さんには独特の「変わらなさ」がある。
私は、彼女の家庭教師をしていた。彼女が中学1年生から高校3年生まで。彼女が当時から小説を書いていたのは知っていた。ただし、きちんと読ませてもらった記憶はない。永井さんが言う。「小説は中学生のときから書いていて、公募などにも出していました。人に読んでもらわないと、文章が良くならないことは分かっていましたし。ただし、身近な人、親しい人には読ませたくなかった。理由は、近い人に読ませて、酷評されたりしたらメンタルダメージが大きいから」
中高と小説を書き続けていた永井さんだが、大学では書く機会が減少したという。「高校までは、自分だけの世界と向き合っていれば良かった。ところが、大学に入ると、人間関係も広まり、用事もいろいろと増えていった。そんななか、どこに焦点を絞って書いていけばいいのか、分からなくなっちゃったんです」
それでも、「学生時代にデビューしたい」という思いは強かったという。「同世代がデビューしていくのを見て焦りが出はじめました。自分は、時代小説で勝負したいけれど、デビューしていく若手作家の多くは現代小説の書き手。迷いが生じました。現代小説か、純文学か、エンタメか、自分が一番大切にしている時代小説なのか。完全なジャンル迷子になっていましたね」

大学卒業後は新聞社に入った。ゼミの先生に「小説家になるにせよ、一度社会に出て働いてみなさい」と言われたからだ。しかし、入ってはみたものの、新聞の仕事が、体にも心にもあわなかった。忙しい毎日のなか、過労で倒れ、新聞記者としてのキャリアはあっという間に終わった。
休養後、永井さんはフリーライターに転身する。「とにかく何か書く仕事をしたくて探した」という。自ら雑誌社に企画を持ち込み、編集者と議論を交わした。企画が採用されたら、記事を書くために、さまざまな人のところに取材に出向いた。そのときの経験が、その後の小説創作に生きてくる。「ベンチャー企業の社長さんにインタビューをしたり、女性芸人との企画のライターをするなど、本当にいろいろな方と会い、話を聞き、それらを文章にしました。そのとき、『人の話を聞くのってこんなにも面白いんだ』と思ったんです。“仕事”を口実に毎日のように、様々なタイプの人に会い、話を聞ける。やめられなくなりました。直木賞をいただいた『木挽町のあだ討ち』は、あだ討ちにかかわった人々が、あるお侍さんのインタビューに応じていく形式の小説です。フリーライター時代の、特にインタビューの経験が生きた作品だと思っています」

そんななか、リーマンショックが社会を襲う。出版界も大きなダメージを被った。「雑誌がバタバタと廃刊になっていきました。フリーランス(のライター)を使わない雑誌も増えてきて……。そんなとき、ふと考えたんですよ。『私、そもそも小説を書きたかったんじゃなかったっけ』って。ライターはやめたくない。でもこのままでは食べていけない。それで思ったんです。兼業でなんとかやっていけないかと。小説を、もう一度、書いてみようと」
ジャンルは、やはり昔から好きだった時代小説に定めた。「学生時代、デビューしたくて悩んでいたところ、小川さんに文芸編集者を紹介してもらって、そのかたに小説をみてもらっていたんです。現代小説、時代小説、短編……。こう言われました。『全部読ませてもらったけれど、現代小説はいやいや書いているのが分かる。永井さん、あなた、時代小説を書きたいんでしょ? 好きなことを書いたほうがいい』。その言葉は今も心のなかにあります」
2010年、永井さんは、小説家デビューを果たす。時代小説、『絡繰り心中』(当初のタイトルは『恋の手本になりにけり』)が小学館文庫大賞を受賞。江戸時代の廓話だった。「学生のころから時代小説が好きで書いてもきたけれど、江戸時代のものは初めてだった。当時の編集さんに『時代小説なら江戸ものしか売れませんよ』と言われて。それでも、とにかく、デビューできたことが大きかった。小川さんには、『えっ、廓話!?』と驚かれましたが」

その後も、様々な時代の歴史小説を書き続けている永井さん。直木賞に輝いた『木挽町のあだ討ち』は、デビュー作と同じ江戸ものだ。しかも、完全な廓話ではないが、吉原に出入りする人物が大勢出演する話。遊郭、芝居小屋、男娼の街……。当時、社会の日陰部分と思われていた場所と深くかかわる人々が、事件(あだ討ち)の証人として、インタビューに応じていく内容。彼らの証言により、事件のあらましが明らかにされていくと同時に、語り部ひとりひとりの人生模様も浮き彫りになっていく。永井さんが続ける。「『木挽町のあだ討ち』は、私が頭のなかで設定した登場人物たちが、勝手に喋り出し出来ていった作品です。なかに、ひとり阿吽の久蔵という語り部がいて、この人物だけがなかなか話してくれなかった。困って困って、最後に彼の奥さん、つまり女将さんを設定して小説のなかにひっぱりだした。そうしたら、この女将さんが話し出してくれたんです。あのときは本当に助かりました」

やはり、ライター時代の取材の経験が生きている。「フリーのころ、まるで野球の千本ノックみたいに、インタビューの仕事をやってきた。そのときに関わったいろいろな人物像のイメージが、まだ頭のなかに残っているんです。小説にリアリティを注ぎ込む際、自分が設定した登場人物に近い人を、今までインタビューしてきた人から探してきたりもします。あの人だったらどうするだろう。きっと、嫌な顔をしそうだな、いや、ここは明るく話してくれるだろう、とか。いろいろ考えながら、キャラを作りあげていくんです」
設定はなるべく細かく、リアリティに留意して。そのために、片山洋次郎さんの「体癖(たいへき)」についての本を参考にしたり、星座同士の相性などをチェックしたりもする。「このキャラだったら、肩で風を切って歩くだろう。こっちの人は背中を丸めがちかな。いろいろと思案しながら、机の前で実際に自分もその仕草をやってみる。そうすると、頭にキャラがスウッと落ちてくることがあるんです。あとはキャラに自由に話してもらえばいい」
永井さんの小説は、ほとんどが、ひとり語りふう(あるいはインタビューふう)の一人称スタイルか、人物ひとりを設定して、その人の目線から世界を眺める三人称スタイルで書かれている。『木挽町のあだ討ち』は前者だが、今後もこうした一人称スタイルの小説を書いていくつもりなのだろうか。「実を言うと、このスタイル、私自身はすごく好きです。一人称小説の場合、補足説明を文章ではなく、人物の台詞のなかに導入できる。映像芸術ではないから、説明は絶対に入れなくてはいけない。一人称の場合、それを“語り”のなかに入れられるのが大きなメリットなんです。だから、ちょっとした短編などでも一人称で書いてみたいな、と思うこともしばしばあります」

文芸学科の“小説家の卵たち”からも鋭い質問が飛ぶ。「フィクションである小説にリアリティを与えるために、どんな工夫をしていますか?」という質問。少し考えてから永井さんは答えはじめた。「ある人にこう言われたことがあります。『(作品に)ゴジラを出すのなら、主人公の住むアパートの家賃はしっかり設定しておけ』と。つまり、コジラという大ウソを出現させるなら、暮らしぶりなどの関する設定はマニアックなほどに細かくしろということなんです。例えば、ファンタジーの異世界の話なら、そこにジャガイモはあるのか。それをちゃんと決めて欲しい。もしジャガイモがあるなら、飢えはないのかもしれないし……。人々が何を食べ、どんな道具を使い、どんな暮らしをしているのか。そのために綿密に取材をするわけです。私は時代小説を書きますが、過去の日本は、今の我々から見れば、“異世界”です。そこで大ウソをつきたい、つまり何かとんでもないものを見せたい演出を考えているなら、きちんと取材をし、細かく設定を決めることです。それによって、フィクシュンにおけるリアリティは必ず高まります」

小説を仕上げるときに気をつけていることは? 「そうですね。書き終えた原稿を音読して、できれば誰かに聞いてもらうといい。私は、原稿ができると家族や犬に向かって音読しています。かの泉鏡花さんもやっていたし、他の作家さんからも『同じことをしている』という声をよく聞きます。校了の時には喉が枯れている人もいるとか……。声を出して読むと、おかしな部分をチェックできる確率が高まるんだと思います」

午後には学生たちを前に『木挽町のあだ討ち』の誕生秘話や登場人物の解説をしてくれた永井さん。最後に、芸大生の印象を語ってくれた。「直木賞受賞後、いろいろな場所で話をさせていただく機会が増えたんですが、大芸大の学生さんの質問は、どこよりも“専門的”でした。普段、小説を書いている人が多いからだろうな、と思いながら、答えていました。私の今日の話が参考になるかどうかわかりませんが、皆さんが創作を進めていく上で、ヒントになるようなことが少しでもあったなら、嬉しいです」





自分が小説を書くとき、キャラクターたちが好き放題に喋り出してしまうことがあり、心配になることがある。永井先生は、むしろそれを使ってキャラクターの個性を作り出していると聞き、素晴らしいと思った。その他、「取材をして本に生かしきれないものがあっても、別の本で生きてくることある」というお話や、「ライトノベルも好きで賞に応募したことがある」という話など、取材や経験、どんなことも無駄にせず創作に生かしているのがすごい。『木挽町のあだ討ち』のキャラクターのなかでは、初代ほたるさんがかっこよくて好きです。