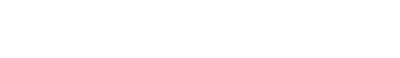舞台芸術学科 学外公演「十一ぴきのネコ」 舞台芸術学科 学外公演「十一ぴきのネコ」

2024年3月16日・17日に、舞台芸術学科の学外公演「十一ぴきのネコ」が、大阪中央区のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて行われました。同公演は、馬場のぼるの絵本をもとにした井上ひさしの戯曲を原作に、仕事や住む家などがなくて腹ペコな野良ネコたちの姿を描く音楽劇。出演者たちの熱のこもった芝居、そして舞台美術、照明、音響など同学科で各分野を専攻する学生たちが作り出した演出により、野良ネコたちが経験する旅がよりスリリングなものになりました。
腹ペコな野良ネコの視点で歌われる曲とダンスの数々

プロ仕様の本格設備を備えた施設「大阪芸術大学 芸術劇場」を学内に構え、舞台に立つ演者たちはもちろんのこと、そのステージを支える専門家なども育成している舞台芸術学科。そんな同学科にとって継続的に実施されている学外公演は、舞台人としての将来につながる貴重な経験になるほか、学内公演ではなかなか味わえない緊張感も学生たちの成長を後押しします。

今回上演された「十一ぴきのネコ」は、井上ひさしの戯曲が原作。主人公は、家、仕事、意気、お金、運など生きるために必要なあらゆるものを持ち合わせていない野良ネコたち。そんなネコたちの口からいつも出るのが「お腹が減った」「ペコペコだ」という言葉。しかしあるとき、遠く離れた星の下に広がる湖に大きな魚が棲んでいることを知ります。食欲に駆られたネコたちはその魚を捕まえるために旅へ出ますが、道中、いろんな困難に直面します。


井上ひさしの原作戯曲では、高度経済成長期を迎えた当時の日本が抱えていた公害問題などが背景として描かれていました。しかし今作では原作戯曲の要素を生かしながら、現代を生きる若者たちの青春模様が重ねられています。自分の居場所は一体どこにあるのか、夢を叶えるためにはどんな道を歩めば良いのか。若者特有の悩みが、野良ネコというキャラクターを通して表現されています。さらに、多彩かつパワー溢れる音楽、ダンスが全編に渡って繰り広げられる点も見どころです。野良ネコの視点で歌われるユニークな楽曲の数々が観客を惹き込んでいきました。

また、舞台美術、照明、音響、衣装などにも目を奪われます。ネコたちの豊かな個性や置かれている状況がそれらからも伝わってきました。特に、ネコたちが魚を捕まえるために船を漕ぐ場面の臨場感はスタッフたちの力量が強く感じられます。約1か月という短い期間で仕上げられた作品とは思えない内容の濃さもあり、笑ったり、話をグッと噛み締めたりする観客の姿も。物語が終わり、カーテンコールに迎えられた演者やスタッフたちは安堵と充実の表情を浮かべていました。

フィナーレではスタッフたちもネコに扮して登場。全員が「十一ぴきのネコ」の世界に入りきっていた。



今回の『十一ぴきのネコ』の各楽曲は、原作の音楽を担当された青島広志さんが作曲した合唱曲集をベースに、それを生かしながらも良い意味でいかに壊していけるかがポイントでした。ある曲では青島さんのピアノアレンジにいろんな要素を飾ったり、またある曲では完全にリビルド(再構築)したり、自分なりに解釈して編曲しました。今回の学外公演のために書き足した6曲については、作品のカラーと合うかどうか非常に悩む部分もありました。そんな中、重視したのは主人公が野良ネコであること。「野生を感じさせるサウンドってどういうものだろう」と考えて作りました。また、「人は一人では生きられない」というメッセージもイメージしながら曲を制作しています。しかし、これらの楽曲を鳴らすのは音響スタッフの学生であり、また歌や演奏で表現するのも学生です。私は『十一ぴきのネコ』の音楽を作る際も、一つの音符、一つの音程にいろんな愛や社会への皮肉を込めています。一方で、学生たちにはそこまでのことは伝えないようにしました。なぜなら「自分で気づく」という経験がこれから舞台をやっていく上では必ず必要だからです。解釈が大きく外れたときは「この一音の意味って分かりますか」と軌道修正しますが、普段は稽古場でも説明しすぎず、学生たちの感性を信用します。そうすることで曲の解釈も深まり、たとえばソロで楽曲を歌う学生も、その曲を愛したり、逆に嫌ったり、いろんな感情の機微を乗せることができるからです。私の幸せは、舞台上からその感情が伝わってきたとき。学生たちには今後もいろんな感情を張りめぐらせながら、人の気持ちもちゃんと理解できる人間になって欲しい。そこで初めて、この作品のテーマ「人は一人では生きられない」に気づくことができるのではないでしょうか。

私は今回、にゃん六という役を演じました。「ダメでもともと。役者、ゴミ箱。天国に帰るだけ」という台詞の泥臭さが好きで、「この役がやりたい」と配役希望を出しました。そんなにゃん六を演じる中で、改めて考えたのが「なぜそういう台詞を言うのか」ということ。私は大阪芸術大学へ入学する前も地方合唱団に所属し、ミュージカルなどへの出演経験がありました。当時は歌い踊ることがただただ楽しかったのですが、大阪芸大で演劇を学ぶ中で、作品への理解や戯曲の読解を深める大切さを知りました。今回の『十一ぴきのネコ』でも、内藤裕敬先生、そして仲間たちの考え方などから気づくことがたくさんあったんです。特に印象的だったのが、内藤先生がおっしゃっていた「役者は、光と音と衣装と美術の良い共演者になれ」という言葉。スタッフの学生のみなさんのこともちゃんと考えて表現しないと、同じ舞台を作り上げることは難しい。しかも『十一ぴきのネコ』は、20人の役者がずっと出ずっぱりで、動きっぱなし。自分のことだけ考えていてはいけません。その点で、この作品でしか味わえない経験がたくさんありました。私が感じる演劇の魅力は、稽古期間にそういう共通理解をみんなで深めていく過程にあると思っています。今回の経験を通して、あらためて「これからも演劇を携わっていきたい」という気持ちが膨らみました。

僕はにゃん次役を務めたのですが、今では自分以外がその役を演じている姿が想像できないくらい愛着が湧きました。劇中「汁かけご飯、一膳」という台詞があるのですが、実は僕もご飯にお味噌汁をかけて食べるのが好きなんです。そういう部分でもにゃん次に親しみがあります。ただ、ギターの生演奏シーンはすごく緊張しました。中村康治先生から「ギターが弾ける人は誰かいますか」と尋ねられたとき、高校時代に軽音部に所属していてギターも演奏できたので立候補しました。ただ、舞台は生もの。「失敗したらどうしよう」という恐怖心が日に日に大きくなっていきました。だけど先生たちが「失敗しても後に引きずるな」とおっしゃってくださったことで、気持ちが軽くなりました。あと先生方の「舞台上で演じている自分を、別の場所から見守るような感覚を持ちなさい」という教えを、本番では常に意識していました。だからたとえ失敗しても、別の場所で見ているもう一人の自分が「続けろ、続けろ」と背中を押してくれるんです。その感覚のおかげで、たとえばやりすぎて演じてしまった場合もちゃんとブレーキがかけられるようになりました。なにより学外公演で実感したのが「舞台上で生きるのっていいな」ということ。見知らぬお客様が笑ったり、拍手をしてくださったりすると、大きな喜びがあります。今後も何らかの形で舞台に携わり、そういう喜びを感じて生きていきたいです。

私は『十一ぴきのネコ』で照明デザイナーを担当し、本番ではオペレーターである3年生の照明スタッフに指示を出す役割を務めました。演者は、本番でお客様が入ると舞台上の動き方も微妙に変化するもの。照明はそういう変化を察して臨機応変に対応しなければなりません。何より作品内容もしっかり理解しなければ、照明は作れないんです。たとえば『十一ぴきのネコ』の物語には、舞台を作る人、売れない役者の感情も重ねられています。その内容に共感した上で、照明スタッフとしてどのように野良ネコたちのことを伝えていくか。基本的には、喋っているネコ、台に乗っているネコなど、目立つ立ち位置のキャラクターに光を当てます。しかしその後ろで別のことをやっているネコたちをどのように表現するかは、照明スタッフの腕の見せどころ。照明は、そうやって一歩引いた立場で作品を見ることも重要です。中学時代、演劇部の兄の公演を鑑賞しに行ったときに照明演出の魅力とそのパワーを感じ「照明の勉強をしたい」と大阪芸術大学に入学しましたが、4年間、いろんなことを勉強すればするほど知りたいことが増えました。卒業後は舞台の技術職への就職が決まっています。そこではまず照明とは違う仕事をやる予定ですが、大学で学んだことは必ず生かせると思います。
Photo Gallery