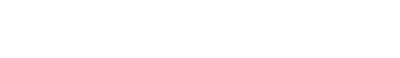Topics
vol.4 居場所を見つける vol.4 居場所を見つける


イラストレーション:石黒正数
1999年4月。春のキャンパスは人でごった返して、フェス会場みたいな活気だった。わたしが専攻した映像学科の同期生は百人ちょっと。大学全体には数千人の学生がいたそうだ。
講義の間はしーんとしていたキャンパスが、昼休みのベルが鳴ると同時に、教室からはき出された学生たちで混沌となる。学食の席はみるみる埋まり、9号館の大階段は、地べたに座り込んだ人で足の踏み場もないくらいになった。とにかく人、人、人。のんびりした田舎からやって来たわたしは、ただでさえ人混みに免疫がなくて、ちょっとまいってしまったくらいだった。
大学は高校と違って、何年何組、みたいに所属する教室がない。だから学生たちはそれぞれ、キャンパスのどこかに、教室の代わりになるような居場所をつくる必要がある。学食の目立つテーブルだったり、サークルの部室だったり、親しくなった教授の研究室だったり、居心地のいい場所は人それぞれ。わたしもいつの間にか、自分の居場所を見つけた。映像学科の研究室がある7号館の、廊下の壁の裏側に、ひっそり隠すようにしつらえられたベンチだ。
わたしと友達はそこを「死角」と呼んで、授業のない手持ち無沙汰な時間は、逃げ隠れるようにして身を潜めた。死角はその名のとおり、廊下を歩いている人が、まさかそこに人間がたむろしてるなんて気づかないようなつくりで、ものすごく日当たりが悪い。だけどすごく落ち着いた。広大な大阪芸大のキャンパスのなかに見つけた、愛しい居場所。たまに先に座っている人がいて死角に陣取れないと、巣穴を追い出されたリスみたいにそわそわしたっけ……。
昼休みは総合体育館のコンビニで弁当を買い、死角で食べて、食後はカフェ・ラッテを飲みながらタバコをふかす。若者特有の厭世的な気分にひたって、ごろんと寝転んだり、写真を撮り合ったり。メインストリームから外れた、この世の果てみたいなところで、気の合う友達とだけの、ひそひそとした時間を過ごした。死角はいまだに、わたしの魂の居場所みたいになってる。
春のうちは学生でごった返したキャンパスも、夏、秋と季節がめぐるごとに、あふれていた人の波が引いて、静かな日常らしいテンションに落ち着いていった。毎年そうだった。春にはキャンパスが人であふれ、ふと気がつくと、人が減っている。あれは新入生がみんな、それぞれの居場所を見つけたってことだったわけだ。
●山内 マリコ(やまうち まりこ)1980年富山県生まれ。作家。大阪芸術大学映像学科卒業。2008年、「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞し、2012年『ここは退屈迎えに来て』でデビュー。同作と『アズミ・ハルコは行方不明』は映画化もされた。2021年には『あのこは貴族』も映画公開予定。『山内マリコの美術館は一人で行く派展』などエッセイも多数。